10月は食品ロス削減月間!

食品ロスの削減を推進する法律により、毎年10月は全国的な啓発期間となり、10月30日は「食品ロス削減の日」と定められいるよ!
しかし「食品ロス」と聞いても、具体的にどれほどの食品が捨てられているのか、実感が湧きにくいかもしれません。
今回は最新データと国の取り組みを見ていきます。
食品ロスの現状 – おにぎり一個分が毎日捨てられている?
まだ食べられるのに捨てられてしまう食品を「食品ロス」といいます。
発生源は大きく分けて、外食産業や小売業者などから出る事業系食品ロスと、作り過ぎや食べ残しによって家庭から出る家庭系食品ロスの2種類です。
農林水産省と環境省の最新推計によると、2023年度の日本の食品ロスは事業系231万トン、家庭系233万トンの合計464万トンでした。
これは国民一人あたり年間約37kg、一日あたりおにぎり一個分(約102g)が捨てられている計算になります。
世界中の飢餓に苦しむ人々に向けた食料支援量が370万トンであることと比べると、日本はそれを上回る食品を捨てていることになり、非常に残念な現状です。
食品ロスの焼却にはCO₂排出も伴い、地球温暖化の原因にもなります。
こうした問題を踏まえ、2019年10月に「食品ロス削減の推進に関する法律」が施行され、政府や自治体、事業者が連携して削減に取り組んでいます。
政府は2030年度までに2000年度比で事業系食品ロスを60%減、家庭系食品ロスを50%減する目標を掲げています。
そして、この法律によって毎年10月が食品ロス削減月間、10月30日が食品ロス削減の日と定められました。
環境省の取り組み – モッテコとデコ活、そしてイベント
今年の食品ロス削減月間では、環境省が消費者庁や農林水産省と連携し、集中的な普及・啓発活動を行っています。具体的な取り組みをいくつか紹介します。
- 自治体職員向け事例集の公開:自治体での成功事例をまとめた「食品ロス削減のための取組事例集」の最新版を10月中に公開し、全国の自治体が情報交換できるようにします。
- mottECO(モッテコ)推進の強化:飲食店で食べ残した料理を持ち帰る行為を親しみやすく呼びかける「mottECO(モッテコ)」の普及を目指し、杉並区・多摩市・千代田区でポスターや専用容器の配布などの実証事業を行います。
- デコ活と食品ロス削減の呼びかけ:脱炭素につながる豊かな暮らしを提案する「デコ活」キャンペーンの一環として食品ロス削減を訴え、国民のライフスタイル転換を後押しします。
- 広報活動:環境省のウェブマガジン「ecojin(エコジン)」では、家庭での食品ロス削減の工夫を紹介する「エコデリキッチン」コーナーを掲載し、子ども向けメディア「エコチル」でも「食品ロスをなくそう」をテーマに特集を組む予定です。
さらに、10月5日(日)には埼玉県越谷市のイオンレイクタウンkazeで、環境省・消費者庁・農林水産省が共同で「“MOTTAINAI®”をはじめようフェス」を開催しました。
食品ロス削減推進アンバサダーであるお笑い芸人のロバート・馬場裕之さんも登壇し、「食品ロスって何?」を学べるトークセッションや、買い物時・保存時・調理時・外食時の各フェーズで食品ロスを減らす工夫を紹介するコーナーなど盛りだくさんです。
消費者庁の取り組み – 全国運動と川柳コンテスト
消費者庁は関係省庁や事業者、学校、団体、自治体などと協力し、食品ロス削減を国民運動として広げています。その方法はポスターやチラシの掲示、テレビやSNSでの情報発信のほか、実際に参加できるイベントやコンテストも用意されています。
- 食品ロス削減ガイドブックの公開:消費者庁はウェブサイトで「食品ロス削減ガイドブック」を提供し、家庭での具体的な工夫や事業者の取り組みを紹介しています。
- 食品ロス削減全国大会:毎年10月30日には、開催自治体や全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会と共同で「食品ロス削減全国大会」を開催し、優れた取り組みを表彰しています。
- 「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテスト:ユーモアあふれる川柳で食品ロス削減を呼びかけるコンテストを実施し、受賞作品はポスターとして公開されます。
- 行動を変える具体策:消費者庁は、商品の陳列棚の手前から期限が近い商品を選ぶ「てまえどり」や、飲食店での食べ残しを持ち帰る「mottECO(もってこ)」の普及に力を入れています。また、余った食品を学校や職場に持ち寄って地域の福祉団体やフードバンクへ寄付する「フードドライブ」活動も広がっています。
今日からできる食品ロス削減のコツ
国や自治体の取り組みを知った上で、私たち一人ひとりができることを見ていきましょう。難しいことではなく、ちょっとした心がけでムダを減らせます。
- 買い物前に献立を考える:冷蔵庫の中身を確認して足りない分だけ購入すれば、余計な食材を買い過ぎません。
- 賞味期限と消費期限を理解する:賞味期限は「おいしく食べられる期限」であり、過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。消費期限は安全に食べられる期限なので、違いを意識して食品を管理しましょう。
- 先入れ先出しを徹底:新しく買った食材を奥に、古いものを手前に置き、古い方から使うと無駄が出ません。
- 余った食材を冷凍保存やリメイクに活用:余った野菜や料理は冷凍保存したり、スープやカレーなどにリメイクして使い切りましょう。
- てまえどりを実践:すぐに食べる予定のものは、陳列棚の手前にある賞味期限の近い商品を選びます。これだけでも店での食品ロス削減に貢献できます。
- 外食時はmottECOを活用:食べ切れなかった料理は持ち帰り用容器で持ち帰り、自宅で美味しく食べる習慣を身につけましょう。
- フードドライブに参加する:家で余った未開封の食品は、地域のフードバンクや福祉団体に寄付することで有効活用できます。
まとめ – 小さな行動から大きな変化へ
日本の食品ロスは年間464万トンという大きな問題ですが、一人ひとりの小さな行動が集まれば、大きな削減につながります。
国は10月を食品ロス削減月間と定め、さまざまな施策やイベントを行っており、消費者庁もガイドブックや全国大会、川柳コンテストなどを通じて行動変容を促しています。

この機会に、買い物の仕方や食卓の習慣を見直し、家庭でもできる食品ロス削減に取り組んでみませんか?
食品ロスを減らすことは、家計の節約になるだけでなく、地球環境や世界の食料問題の改善にもつながります。10月の食品ロス削減月間をきっかけに、あなたもムダゼロを始めてみましょう

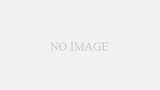
コメント